NO SIDE 第1話~第5話
- 2019.09.09
- 未分類

第1話~プロローグ~
何度も夢見ていたチャペルの前に僕は立っていた。
「ここで結婚式あげようね」
チャペルの前を通るたびに言っていたミウの言葉が聞こえた。
そしてその時の彼女の笑顔も一緒に思い出した。
しかし、彼女は僕ではない別の男を選んだ。
僕はミウから何を奪ってしまったのだろう。
そして何を与える事ができなかったのだろうか?
今日はミウの結婚式だ。
今まさにこの中に幸せを願う彼女がいる。
そして僕はそんな彼女を見届けにきた。
初めて触れるチャペルの扉は大きかった。
扉を開けて中に入る。
さっきまでかすかに聞こえていたオルガンの響きが
リアルな大きさになった。
扉が開いた音に驚いて、いくつかの目が僕を見た。
でもそれは一瞬で、すぐにその視線も祭壇の二人に戻った。
「ミウ…」
ウエディング姿の彼女は確かにそこにいた。
牧師に向かって立っている彼女の姿は、
僕が思っていたよりずいぶん小さく見えた。
「ミウ」
いつの間にか僕は声を出して彼女を呼んでいた。
しかしその声は彼女までは届かない。
セレモニーはクライマックスの指輪の交換になった。
彼女が彼と向かい合う。
彼女の横顔…そこには僕の知らないミウの顔があった。
あんな表情の彼女を僕は見た事がない。
「ミウ!」
いつの間にか僕は大声をあげていた。
なぜ僕は彼女を呼んでいる?
彼女に僕の存在を気づかせて、そしてどうなるんだ?
しかしそんな僕の存在を認めないかのように、
チャペルに集まっている人たちは僕を見ない。
そして指輪の交換は何事もないように続く。
ミウにはめられた指輪…そしてミウから彼に。
「ミウ!!」
僕はさらに声をあげた。
その時、ミウが僕を見た。
(気づいてくれた!)
何かを期待していたわけではない。
ミウに僕の存在を気づかせて、
僕は彼女を試したのかもしれない。
しかし彼女の顔は、その表情は何も変わらない。
彼女は僕を見ても、何事もなかったように
彼の指にリングをはめたのだ。
そうだ、もう終わった事なのだ。
僕だけの時間が止まっていたのだ。
ミウは僕とじゃない新しい幸せを選んだのだ。
僕は振り返りチャペルの扉を開けて外に出た。
外の光は眩しかった。
それは本当に巨大な光で、僕を包み込んだ。
「…ミウ」
そして僕の意識は遠のいた。
第2話~出会い~
どのくらい眠っていたのだろう?
やたらに眩しい光と、気だるい程の暑さ、
そして子供達の遊ぶ声で目が覚めた。
「…」
まるで僕の頭の中は考える事を拒否するかのように止まったままで、
そして僕の体は自由を奪われていた。
(…か、からだが動かない)
それにしてもここはどこだろう?
目に映るのは、太陽の眩しい光と緑…、
突然、僕の顔を覗き込む影でその光が遮られた。
「気づいた…気づいたの?」
その影は人の顔だった。
(…誰かがそばにいる。誰だ?)
「よかった。なかなか起きないから心配したよ」
ようやく動き出した僕の頭で考えても、
その声に聞き覚えはない。
(…誰?)
少しづつ僕を覗いている顔が見え始める。
(女だ…、誰?)
知らない女性だった。
知らない女性の顔が僕を心配そうに見ていた。
「…きみ誰?」
「あっ…、やっとしゃべったね。大丈夫?ずいぶん気を失ってたよ」
僕の質問には答えずにその女性は僕の頭にのせてあった
ハンカチを取るとその場を離れていった。
まだハッキリとは戻らない視線でその彼女を追う。
彼女は近くにある水飲み場でハンカチを濡らしていた。
どうやらここは公園らしい。僕は公園のベンチにねているのだ。
辺りを見渡すと、数人の子供たちと
その親と思われる女性の姿が目に映った。
まったく記憶に無い公園だ。
そんな事を考えている僕の頭が急にひんやりとした。
彼女が戻ってきて冷やしたハンカチを頭にのせたのだ。
「…ありがとう」
とりあえずといった感じで僕は礼を言った。
「少し顔色良くなってきたね。ここがどこだかわかる?」
「公園…、でもなんでここにいるんだ?」
「わからないの?あなたここにずっと倒れてたわよ」
「ここに…?なんでここに」
「知らないけど、私のお気に入りのベンチに
あなたが気を失ってたからビックリして…。
とりあえず頭だけでも冷やそうと思って…」
「そっか…。ありがとう」
「どういたしまして…。何も覚えてないの?」
「…覚えてない」
僕は何をしてたのか?
何で気を失っていたのか?
思い出そうとする僕の中にチャペルの映像が蘇ってきた。
(そうだ…、チャペル、ミウ、結婚式)
僕はミウの結婚式を見届けにチャペルに行ったんだ。
そしてウエディング姿のミウを見て、
僕を見ても何も感じていないようなミウの目を見て、
そしてチャペルを出て…その後気を失ったんだ。
(…でもなぜここに?)
ここにいる理由がどうしてもわからなかった。
(まあ、そんな事はどうでもいいか)
道に倒れていた僕を見かねて、ここまで運んでくれた人がいるのだろう。
少し楽になった僕は体を起こし、あらためてとなりの彼女を見た。
やはり知らない女性だった。
「起きて大丈夫?」
「うん。少し楽になった。ごめん…君は誰」
「私…私はセナ。セナよ」
それが、僕とセナの出会いだった。
第3話~セナ~
「セナ…さん?」
「そうセナよ」
「初めましてだよね?」
「…そうね。ねぇ、まだあまり喋らない方がいいんじゃない?」
「大丈夫。だいぶ気分は良くなったよ」
そう言った僕の顔を見て、彼女は微笑むと立ち上がった。
「それにしてもいい天気…。本当に気持ちいいね」
彼女に言われて、あらためて辺りを眺めてみる。
本当だ。こんなに気持ちの良い天気の日だったのだ。
(…ミウの結婚式、晴れてよかったな)
思わず僕はそんな事を考えていた。
ミウはアメオンナなので、
デートらしいデートの時はほとんど雨だった。
だから大切な結婚式の日は
雨の少ない季節を選ぼうといつも二人で話をしていた。
「ねぇ…本当に大丈夫?」
そんな事を思い出して黙り込んでた僕を
いつのまにか彼女が心配そうに覗き込んでいた。
「…ごめん。大丈夫。ちょっと思い出した事があって」
「こんな事聞いていいかわからないけど、
何があったの?本当に顔色悪いよ」
「…うん」
「つらいんだったらさ、話してみてよ。
力にはなれないかもしれないけど、
話を聞いてあげる事はできるから…。
きっと話せば楽になれるよ」
(…そうなのかな?)
「初めてあった私には、とても話せないような事?」
「そんな事はないけど」
不思議だった。彼女には会ったばかりなのに、
僕は彼女に自分の事を話してもいい気分になっていた。
(…初めて会った気がしないな)
あらためて彼女の顔を見ても
やはり僕の記憶の中に彼女はいなかった。
「なに?」
「あのさ、セナさんと会うのって本当に初めてだよね?」
「そうだと思うけど」
「そうだよね…。初めてだよね」
「…私って普通だから、似たような人が世の中にいっぱいいるのだと思う。
きっとその中の誰かと間違えているんじゃない。
…そうだ、あなた名前は?」
「僕はトキヤ」
「トキヤさんね。
ねぇトキヤさん、話してみて。あなたがそんなに苦しんでいる事」
「…実は、今日…」
そして僕は彼女にミウの結婚式での事を話した。
結婚を約束していた女性が、今日別の男と結婚したこと、
僕がその会場に乗込んでいった事、
ミウが僕に気づいても、何も感じなかったこと…。
彼女は黙って僕の話を聞いてくれた。
一方的に喋りまくっている僕の話を
何も言わずに黙って聞いてくれている事がありがたかった。
僕の話が終わっても、彼女はただ僕を見ていてくれた。
どのくらいの時間が過ぎたのだろう。
いつの間にか遊んでいた子供たちもいなくなっていた。
「話してくれてありがとう。どう、少しは楽になった?」
「…そうだね。少しは楽になったかな」
「あのね。ミウさんとはどこで出会ったの?」
「…ミウと出会ったのは大学だよ」
「そっか大学なんだ…。ねぇ、その時の話も聞かせてよ」
「えっ、出会った時の話を…なんで?」
「いいじゃない。いろいろ話を聞いてみれば、
ミウさんの気持ちがわかるかもしれないし…
いいアドバイスできるかもよ」
そう言って、少し悪戯っぽく彼女は微笑んだ。
そして僕は彼女にのせられるままに、
ミウとの出会いを話し始めた。
後から考えれば、僕からミウの話を聞くことは
セナの計画通りだったのだろう。
ただ全てがわかった今でも、
僕はあの時のセナに感謝している。
あの時セナに会わなかったら、
会って話をしなかったら、
きっと僕はずっと真実を知ることができずに
苦しみ続けたと思うから。
第4話~はじまり~
1995年 4月
4月だというのにやけに蒸暑い。
今日は最初の授業なので、
気に入っている上着を着ていこうと思ったが、
この暑さでは、ちょっと無理そうだ。
大学にストレートで受かった事を
誰よりも喜んでいたのは父だった。
自分が大学に行けずに、
今の会社で自分の力が
学歴以上に評価されていない事を何より悔やんでいた。
だから自分の息子には「大学卒」という肩書きを
どうしても付けたかったらしい。
ただその進学する大学をどうするかという事に関しては、
随分と僕と衝突しあった。
僕は特別な大学に進むよりも、
一般大学に進学する事を希望していた。
父は僕が小さい頃より続けていた
ピアノの技術を生かせる大学に進むべきだと主張していた。
僕は特別自分にピアノのセンスがあるとは思えなかったので、
受験に苦労する事がわかりきっていた
音楽大学への進学には躊躇していた。
しかし、父親の情熱に折れる形で音楽大学を受験。
どういうわけか、ストレートで受かる事ができた。
そして入学式も無事に終わり、
今日は本当の意味の大学生活が始まる日だ。
大学のある池袋に到着した。
行きの電車はものすごいラッシュだった。
これから、あの地獄の電車に
毎日のように乗ることを考えると憂鬱だ。
池袋と言っても大学は郊外にある。
そこまでの道のりは都内とはいえ緑にあふれ、
なかなか気持ちが良い。
大学に到着すると、まず今日の講義の教室を探す。
「音楽社会学」という、どう考えてもつまらなそうな講義が
記念すべき最初の授業だ。
この時間に来ているのは、1年生くらいだと思うが、
思ったよりも学生の数が多かった。
講義の行われる教室に到着。
(…ああ、この教室か)
この部屋には見覚えがあった。
夏の講習会の時に待ち合いスペースとして使っていた場所だ。
そういえば、あの時ここで待機していた男たちと口論になった。
あの時の男たちは、ここを受験して受かったのだろうか?
教室を見渡して見たが、それらしき連中はいなかった。
(ちゃらついた奴らだったから不合格だったか?)
どうでもいい事だったが、顔を合わせるのも面倒くさかったので、
見当たらないことに安堵した。
座る場所はどこでも良いらしい。
僕は窓際のなるべく後ろの方の席に座り、
講義が始まるのを待っていた。
「ねぇ」
突然僕にかけられた声に驚いた。
僕の席のとなりに一人の女性が立っていた。
ちょっと気の強そうなつり上がった目が印象的だ。
(…化粧が濃すぎ)
そんな感想を思っていた僕を睨み付けながら
「そこ、どいてくれない?」と想像もしてなかった事を言った。
「えっ?なんで?」
「そこ、私の席なんだよね」
「…?。席って好きなとこ座っていいんじゃないの?」
「そうだけど、そこは私の席なの」
「何?何言ってんの?席なんて決まってないじゃん」
「決まってるのよ。ここはわ・た・しの席なの」
するとその女性は机の上を指差した。
指差された場所を見て見ると、小さい字で
(ミウ)
と書かれていた。
「これが何?」
「ミウって書いてあるでしょ。これ私の名前。
夏の講習の時から、この場所で講義を受けるって決めてたの。
これがその証拠よ…わかったら、どいてくれる」
(なんなんだ、この女)
僕は相当ムカついていたが、
通学初日からこの女性とやりあう気力もなかった。
仕方なく僕はひとつ後ろの席にまわった。
その女性はそんな僕に礼を言うことなく、
僕のいた席に座り平然としている。
こんなに我儘な女性を見るのは初めてだった。
このように、ミウに対する僕の第一印象は
最悪だった。
第5話~そして1ヶ月が過ぎて~
その後もミウの事が気にならなかったと言えば
嘘になるかもしれない。
あんなに強引で我の強い女性は
初めてだったので、強烈に僕の印象には残った。
あの教室で講義がある日は
ミウが例の席に座っているかどうか
一応は確認していた。
だからといって、
それ以上の特別な感情が芽生えたわけではなかった。
大学生となった初めの1ヶ月は、
あっという間に終わった。
自分が思っていたよりも男の同級生が多かった。
もっと女性ばかりのキャンパスをイメージしていたので、
かなり意外ではあった。
そうは言っても数少ない男同士、
すぐに仲良くなった。
中でも猪俣という同じ科の奴とは、
お互いクラシックよりもロックが好きという
意見で意気投合して、色々な事が話せる仲になった。
「おい、三杉」
「…なに?猪俣」
「お前さ、ここら辺でいい喫茶店探してたじゃん」
「ああ」
「俺見つけたぜ。いい喫茶店。今日行ってみないか?」
僕は大学生になったら、
学校の近くでくつろげる喫茶店を探していた。
行きつけの喫茶店をつくることが
僕のささやかな一つの夢だった。
そんな話を最初の頃猪俣に話していたので、
見つけてくれたらしい。
その日の授業が終わると
僕は猪俣と一緒に、そのお勧めの喫茶店に向かった。
その店の場所は大学より池袋駅とは反対の方に
さらに緑の中を歩いていく中にあった。
この辺りでは珍しい、ロッジ風の外観のお店だった。
「…どうよ?いい感じでしょ」
「そうだな。お前にしてはセンス良さそうだな」
「なんだよそれ…。まあいいか、中入ろうぜ」
猪俣を先頭に店の中に入る。
中は外観に比べて狭く感じた。
でもその店内の雰囲気は悪くない感じだった。
本当はカウンターに座りたかったが、
最初からそこに座るのは抵抗があったので、
僕たちは入ってすぐの席に座った。
店内のBGMはジャズだった。
(…このピアノはオスカー・ピーターソンだな)
悪くない選曲だった。
「いらっしゃい」
この空間にピッタリの風貌の
マスターらしき人が水を運んできた。
その人は猪俣の方を見て
「この前も来てくれたね。ありがとう」と話しかけてきた。
「マスター、彼は三杉トキヤ。大学に入って初めて出来た友達」
と猪俣が僕のことを紹介した。
「三杉くんか。今日はありがとう」
「いいえ…。素敵な店ですね。外観もBGMも中も素敵ですよ」
「そうかい?ありがとう。後はコーヒーが合格ならいいけどね」
「その点は俺が保証します。マスターのコーヒー最高です」
すかさず猪俣がそう言った。
マスターは柔らかい微笑で僕たちを見て
「じゃあコーヒーでいいかな?」と言いながらカウンターに戻っていった。
コーヒーがくるまでの間、猪俣と学校についての他愛の無い話をしていた。
時間が半端なのか、僕と猪俣以外には誰もいない。
店には悪いが、それも僕にとっては気に入る喫茶店のポイントだった。
その時突然扉が開き、僕たちの静寂な空間がかき消された。
「マスター、ごめんね!遅くなっちゃった」
中に入ってくると同時にデリカシーのない大声で
マスターに向かって歩いていく。
その声には聞き覚えがあった。
「ミウちゃん。お客さんがいるんだよ」
マスターの嗜める声。
そう…それはミウだった。
-
前の記事

パーティーの余興にゴスペルを 2019.09.04
-
次の記事
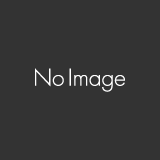
NO SIDE 第6話~第12話 2019.09.11
