NO SIDE 第6話~第12話
- 2019.09.11
- 未分類

第6話~なぜ?~
「お待たせしました」
コーヒーを運んできたのはミウだった。
「こんにちは。たしか同じ大学だよね?」
猪俣がミウに話かけた。
「そう…?同じ大学なの?」
(…すぐに気づけよ)と思いながら
僕はミウにたずねた。
「…僕にさ、見覚えない?」
「…あっ!」
「思い出してくれたか…。
初対面でいきなり席を奪われた男のこと」
「そうだったわね。あの時はありがとうね」
何故かミウは(ごめんなさい)ではなく、
(ありがとう)という言葉を使った。
僕は少し意外な感じがした。
「ここでバイトしてるんだ?」
「そうよ。7時くらいまでね」
「音大のお嬢様でもバイトするんだ。
…何?社会勉強?」
僕は自分でも考えられないほど、
ミウに対してきつい言葉を投げた。
「なによ…。まだあのこと根に持ってるの?
悪いけど私、お嬢様じゃないわよ」
猪俣は驚いた表情で僕たちのやりとりを見ながら、
「なにお前ら…知り合いだったの?」と言った。
「記念すべき最初の講義で、いきなりガンをつけられたんだよ」
「品のない言い方ね。
あなたが勝手に私の席に座ったからでしょ」
「…だから、なんであの席が君の席なんだ?」
「いいじゃない別に理由なんて。
たまたまあなただったけど、誰が座ってても
私は同じことをしたわよ」
「どいてもらうのでもさ、言い方があるじゃないか。
あれじゃまるで喧嘩売ってるみたいだ」
「もう!しつこいな。
さっき(ありがとう)ってお礼言ったし、もういいでしょ」
ミウと僕のやりとりを黙って聞いていた猪俣が
「あのさ…。せっかくこうして会ったんだし、
楽しくやらないか?」とあきれたように言った。
考えてみれば猪俣の言うとおりだった。
この一ヶ月、あの席に座れないことなど
たいして気にもしてなかったはずだ。
ただ、こうしてミウに会って話をしてみると、
なぜか自分の中で思ってもいない言葉が溢れてきてしまった。
「…そうね、同じ大学同士だもんね。
…わたしミウよ。梶本ミウ」
「俺、猪俣 大」
「…三杉トキヤ」
そんな自己紹介が終わった時、
新しい客が店内に入ってきた。
(いらしゃいませ)と言いながら
ミウはカウンターに戻っていった。
僕はそんな彼女を目で追いながら、
彼女が運んできたコーヒーに口をつけた。
「どうよ?」
「…なんだろうな…。初対面があまりに悪かったからな。
…でもバイトしてるのは意外だった。
どうせそんな必要もないお嬢様だと思ってたからさ。
入学してまだ一ヶ月だろう…
もうバイトしてるって、なんか理由があるのかな?
それにしてもさ、本当に気の強い女だよな。
顔にも出てるっていうか…。
最初の時も思ったけど、あんな女初めてだよ。
ここのマスターも大変だよな。
あんなの雇っちゃってさ」
一方的に捲くし立てる僕を見ながら、
猪俣はあきれた顔で言った。
「…俺が聞いてるのは、コーヒーの味なんだけど」
苦笑している猪俣の顔を
まともに見れない僕がいた。
第7話~そして再び~
話し始めてみたら思っていたよりも
スムーズに話をすることができた。
それはきっと隣で聞いてくれているセナさんが、
ちゃんと話を聞いてくれていたからだろう。
彼女は真直ぐに僕を見ていた。
そして目をそらさずに僕の話を聞いてくれた。
時おり微笑んだり、頷いたり首をかしげたり、
ちゃんと僕と向いあってくれていた。
考えてみればミオを失ってから
こんな風に誰かと向かい合って
話すことなどなかったのだ。
「そっか…。二人の出会いは最悪だったわけだ」
「そうだったんだ。
ミウは今まで僕が知っている女性の誰よりも
最低の印象だった」
「でもあなたの中に強烈なイメージを
残したわけね」
「そうだと思う。普通に出会っただけだったら、
もしかしたら好きにならなかったかもしれない」
「なんかわかるなぁ、その気持ち。
最初のイメージは良すぎるか悪すぎる方が
きっと後でいろいろな発展があるんだろうね」
そして彼女は少し寂しそうに微笑んで言った。
「その点私なんかダメだわ。すごく普通だもの」
「そんなことないよ。僕は初めて会って、
こんなに楽な気持ちでいられる女性は初めてだよ。
それもすごく印象的なことだと思う」
「…ありがとう」
何かとても嬉しそうに彼女は微笑んだ。
あまりにも僕たちが座っていたベンチでは暑いので、
僕と彼女は公園の近くのカフェに移動した。
今ではあたりまえのように見かけるカフェだが、
僕の学生の頃にはなかった風景だ。
コーヒーが飲みたければ、ミウがバイトしていたような
喫茶店に行くしかなかった。
そしてそんな喫茶店でコーヒーを飲むことが
ステイタスでもあった。
カフェはどこへ行っても同じ味を楽しめる
安心感はあるが、何か物足りなさを感じる。
喫茶店のコーヒーは、その店により味が違った。
初めての店では、どんなコーヒーが出てくるのかが
本当に楽しみで、あの待っている時の時間は
かけがえのないものだった。
けして安くない飲み物だったので、
味がハズレた時には、本当にがっかりしたものだ。
「あの頃はこんな風に気楽に
コーヒーが飲めるなんて考えられなかったよ」
彼女はそんな他愛のない話でも
真剣に聞いてくれた。
「そうね…。私、あなたと同じくらいの年齢だと思うから、
なんとなくその気持ちがわかるわ」
「…セナさんて何歳なの?」
「初めて会った女性に年齢を聞くのは
ルール違反よ」
「そうだね。…失礼だよね」
「ねぇ…。続きを話してよ。
そんな二人が、なぜつきあうようになったのか。
すごく知りたいわ」
「ミウとつきあうようになったのは、
そうだな…、きっかけは雨かな」
そして僕は再び1995年に戻った。
第8話~6月~
6月になった。
今年はいつもより早く梅雨がやってきた。
そして雨の日の多い6月だった。
この頃になると僕もすっかり
大学生活に慣れていた。
ピアノ専攻以外の科の知り合いも増えた。
大学にはピアノやバイオリンなどの楽器専攻以外に、
声楽、作曲、指揮、教育など多くの科がある。
中でも声楽や教育の連中は同じ講義を受ける事が多く、
男女問わず仲良く接する機会が増えた。
そんなわけで入学前にイメージしていた
大学生活に近づいた毎日を僕は過ごしていた。
ただそんな僕には、6月に入り気になる事があった。
ミウの姿を見かけなくなったのだ。
もっとも僕とミウは全て同じ講義を
選択していたわけではない。
ミウの姿を見かけないことは今までもあった。
ただ、あの「ミウの席」のある教室では
いつも同じ講義を受けていて、
必ずミウの事を目にしていたのだが、
最近は、その教室でもミウの姿を
見かけない日が多くなった。
ある日講義が始まっても
ミウがあらわれない事を確認して、
僕は「ミウの席」に座ってみた。
…あの日以来だった。
例のミウと書かれた落書きは残っていた。
なぜ彼女はこの席にこだわるのかを考えていた。
(夏の講習から決めていた)と言っていた
ミウの言葉を思い出した。
あの時に何があったのだろうか?
この席に彼女を繋ぎ止めるほどの
大きな出来事があったのだろうか?
僕も夏の講習には参加していたが、
その時にはミウの事など知らなかったので
彼女に何があったとしても知る術はない。
その日ピアノのレッスンが終わり、
僕はあの喫茶店に向かった。
猪俣と一緒に行ったあの日以来、
3日に一度は通うようになっていた。
それは純粋にコーヒーの味が気に入ったわけで、
ミウに会うために通っていたわけではない。
店に着いて驚いた事にミウはバイトをしていた。
「学校休んでもバイトはしてるんだ?」
注文を聞きにきたミウに尋ねる。
「まあね…。私のことチェックしてるわけ?」
「今日は音楽社会学があったろう。
そりゃ、あの席は気になるからさ…」
「ちょっとね、色々とあって」
「一年のうちに単位落とすと後がきつくなるぞ」
「そんなことはわかってるよ。事情があるの」
「バイトはしてるじゃないか」
「それも事情があるの…。いつものコーヒーでいいの?」
「あのさ…、もう少し楽になったら?
そうやって突っ張っていると疲れないか?」
僕の言葉には答えずにミウはカウンターに戻っていった。
僕はそれ以上の詮索をやめた。
数日がたった。
その日も朝から雨が降り続いていた。
その日の講義が終わると、
明日の講義の確認をするために
入口近くにある掲示板に向かった。
大学にはその辺りに大きな傘置き場が設置されている。
ほとんどの講義がその校舎で行われるため、
学生のためにそんなバカでかい傘置き場を
設置したと思うが、
ほとんどの学生が教室まで傘を持ち込むため
意味のないものだった。
むしろベンチ代わりにその傘たてに腰を下ろし、
話し込む学生の姿が多く見られた。
掲示板を確認していると、
その傘たてにミウの姿を見つけた。
いつもならバイトをしている時間だと思うが、
傘たてに腰掛けてぼんやりしていた。
何となく元気がないように見える。
そんなミウの姿を見るのは初めてなので、
思わず僕はミウに話しかけていた。
第9話~突然のデート~
「こんなところで何してるんだ?」
「…あっ」
「バイトは?」
「今日は休んだ」
「何で?」
「別に…」
「なんだよ、また秘密か…。別にいいけどさ」
僕はミウと並んで傘たてに座ってみる。
「へぇ…、初めて座ってみたけど、
ここに座っている奴らの気持ちが何となくわかるな」
ミウはとなりに座った僕を見て
嫌がっている感じではなかった。
とは言っても歓迎している感じもない。
「三杉くん…。今日これから時間ある?」
「今日?後は帰るだけだから時間はあるけど」
「じゃあ、ちょっとつきあってくれる?」
ミウとつきあうようになって
なぜあの時ミウがあの場所にいたのか聞いた事がある。
「あなたを待っていたのよ」
偶然ではないとミウは言っていた。
それが本当かどうかは今でもわからない。
ただあの日、あの場所でミウと会ったことが、
それからの僕の人生を大きく変えた事は
間違いない。
「ついてきて」
とミウが先を歩き出す。
傘にあたる雨音を妙に大きく感じながら
ただ黙って僕たちは歩いた。
池袋の駅に着くと、ミウは僕の分の切符を買い
僕に渡した。
「どこに行くんだ?」
大学を出て初めて僕がしゃべった言葉だった。
「西武線に乗っていくわ。とにかくついてきて」
ミウはそれ以上何も言わなかった。
初めて乗った西武線だったが、
行き先のわからない僕は
落ち着いてその事を楽しむ気分ではなかった。
電車の中でもミウと僕は何も話さなかった。
ミウはただ流れる景色を見て、
僕は電車内の広告に目を移していた。
20分くらい乗っただろうか、
ある駅に到着した。
「ここで降りるよ」
というミウの声に促され、僕たちは電車を降りる。
もちろん知らない駅だった。
「…どこここ?まだ東京?」
「東京だよ。ここからあとちょっと歩くよ」
「…」
駅を出て初めて通る商店街をぬけていく。
ミウは急いでいるのか、早足で歩いていくので
彼女の後をつけるのが精一杯で
ゆっくりと町並みを楽しむ事はできなかった。
10分くらい歩いたろうか、やがて一軒の家の前に着く。
「着いたよ」というミウの声。
「…えっ?どこなのここは?」
「わたしの家よ。入って」
「えっ、家?なに、どうゆうこと?」
僕はあらためて目の前の家を見る。
見慣れないちょうちんが軒先に下がっている。
よく見ると花も飾ってある。
(…葬式?)
ミウに何か尋ねようとしたが、
僕に構わず家の中に入っていく彼女を見て
あわてて僕も家の中に入った。
「ミウちゃん遅いよ!もう始まるよ」
中年の女性が少し怒った顔で僕たちを迎えた。
「ごめんね、おばさん。ちょっと学校で遅くなっちゃた」
「あなたがいないと、おばあちゃん寂しがるでしょ」
「そうだね。ごめん」
「あら…、そちらの人は?」
ようやくその女性は僕の存在に気づいた。
「大学の友だち。今日ピアノ弾いてもらうから」
(えっ!ピアノ?…なに?)
「あら、それはすみませんね。
ミウちゃんの歌に見送られるのが
夢でしたから、おばあちゃんきっと喜ぶわ。
どうぞあがってください」
僕はひどく混乱していた。
ここはミウの家で、おばあちゃんの葬式らしく、
そして僕がピアノを弾く…?
わけがわからないまま、
僕は家の中に入っていった。
第10話~突然のデート2~
それは、小さなお葬式だった。
参列していた人数は20名くらい。
後でミウに聞いたら身内ではなく、
近所の人や、おばあさんの友達らしい。
坊さんのお経が始まり、焼香が始まった頃に
ミウが僕のところに楽譜を持ってきた。
「これ…。すぐ弾けるでしょ?」
「…まぁ、これくらいなら」
渡された楽譜はジャンニスキッキの
「私のお父さん」だった。
「じゃあ、お願いね。お経が終わったら演奏するから」
「あのさ…。ピアノを弾くのはいいんだけど…。
これは何?君のおばあさんの葬式?
なんで僕を連れてきたんだ?」
「ごめん、後で話すから…。
ピアノお願い。ばあちゃんの大好きな曲だったから」
そう言うとミウは自分の席に戻っていった。
そして…、演奏は無事終わった。
ミウの歌声を初めて聞いた。
とても澄んだ美しい声だった。
ドラマチックなアリアを歌うには、
物足りない声質だと思うが、
チャペルで賛美歌など歌わしたら、
とてもピッタリくると思う声だった。
そしてその歌声は、
僕にとってはとても心地の良い声だった。
その日の葬式は、ミウの歌で終了だった。
通常であれば、火葬場に向けて
出棺をするのだろうが、
今日はお経をあげてもらうだけという事だった。
そういえば、今日この場所に
ミウの両親らしい人を見かけなかった。
当然、おばあさんの葬式なら、
両親を始め、身内の人が参列していて
おかしくはない。
参列の人が皆帰り、
ようやく家の中は僕たち3人になった。
ミウのおばさんが飲み物を持ってきたので、
ようやく僕たちは落ち着くことができた。
「三杉くん、ご苦労様でした」
「うん、君もお疲れ様」
「ピアノありがとうね。歌いやすかったよ」
「あの曲は知っていたからね。
知らない曲だったら、無理だったと思うよ。
初見はあまり得意じゃないんだ。」
「そう?何でもさらっと弾いてしまいそうだけど」
「そんなわけないだろ…。
ところで、君の声いい声だね」
「本当?先生にはもっと迫力出して歌いなさいって
言われてばっかりだけど」
「いいんじゃないの。皆が皆同じように
声を張り上げて歌えばいいってもんじゃないでしょ」
「そう言ってくれると嬉しいけど」
家の中で見るミウは、
学校や喫茶店で見るミウと比べて、
すごくやわらかい感じがした。
そして、そんなミウの方が
何か自然に感じられた。
そして僕は、
そんなミウが少し
愛しいと思っていた。
第11話~突然のデート3~
ミウのおばさんは、黙って僕たちの会話を
聞いていたが、飲み物がなくなったのを見ると、
新しい飲み物を持ってきた。
「ありがとう、おばさん」
「ミウちゃんさ…、これからどうするの?」
「そうだね…。とりあえずここには住めそうだから、
もっとバイトを増やして…、何とか大学は続けるわ」
僕はずっと気になっていたことを
ミウに聞いてみた。
「あのさ…。ミウのご両親は?」
その質問には、ミウではなく、
おばさんが答えた。
「ミウちゃんの両親は、ミウちゃんが中学の時に
亡くなっているの」
「えっ!…両親ともですか?」
「そう。不幸な事故でね。
それからミウちゃんは、おばあちゃんと
ずっと二人で暮らしてきたのよ。
こう見えてこの子、苦労してんのよ」
「それじゃ、おばあちゃんが亡くなってしまったら…」
「そう…。一人になっちゃたね。ミウちゃん」
そんなおばさんの言葉にミウは、
「私は大丈夫よ。
おばさんが近くにいてくれるし、
おばあちゃんがいなくなって寂しくないって言えば
ウソになるけど…、私は大丈夫」
と自分に言い聞かせるように言った。
そしてまた一言「大丈夫」と繰り返した。
(…バイトしていたのは、学費のためだったのか)
僕はなぜミウが外で強がっているのか
わかったような気がした。
彼女はきっと甘える事が出来ないのだ。
自分が生きていくことに必死なのだ。
だから、強がることで心のバランスを
保っているのだと思った。
きっと自分のエリアの中に誰かが入ってきたら、
というより、誰かをそこに入れてしまったら、
自分が壊れてしまうという思いで、
あんなに強がっていたのではないかと。
僕はミウの家からの帰り道、
ずっとそんな事を考えていた。
そんなミウの心を知ってしまったあの時に、
きっと僕はミウに恋をしたのだと思う。
第12話~真実1~
私は彼がトイレに行っている隙に
録音用のテープを交換した。
それにしても彼の思い出の話は
ストーリーとしては完璧だった。
ミウとの出会いから、彼女に恋をするまで、
細かい彼女とのやりとりなど、
しっかりと覚えていた。
(…なのになぜ?)
私はすっかりと冷めた残りのコーヒーに
口をつけた。
「やあ、セナさん」
突然自分にかけられた声に驚いて振り向くと、
そこには小野田先生が立っていた。
「先生…。ここにいたのですか?」
「うむ。君の事が心配でね。
君の事だから、きっとここに来ると思って、
先回りしていたんだ」
「そうですか」
「どうだね、トキヤくんは?」
「本題に入るのはこれからですけど、
チャペルに行くのは、
少し早すぎたかもしれませんね」
「仕方ないよ。彼はまだ事実を
知らないのだからね」
「そうですね…。
先生、彼はあの事実を
受け止められるでしょうか?」
「そうだな…。君次第じゃないかな」
「わたし次第…ですか?」
「うむ。
ただ彼が事実を知ったところで、
君がつらくなるのではないかと
心配だよ」
「先生、ありがとうございます。
でも私のことはいいです。
彼が事実を受け止めて、
そして…」
(そう…。それが私の役目だ)
「そうか…。彼の事は頼んだよ。
あまりあせらないで、
ゆっくりと彼とつきあってあげなさい」
「…はい」
先生の言うとおりだと思った。
彼が事実を知れば、
彼は本当に苦しむだろう。
そして私の気持ちは、
きっと永遠に報われない。
それはよくわかっている。
でも…。
(これでいいんだよね、ミウ?)
(彼が事実を受け止めて先に進む事が、
あなたの望みよね?)
今となっては、ミウの気持ちを
確認する事はできない。
でもきっと彼女なら、
私と同じ選択をしただろう。
「おまたせしました」
彼がトイレから戻ってきた。
そして私は再び、
彼と未来へ歩きはじめた。
-
前の記事
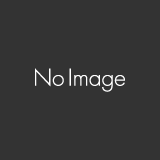
NO SIDE 第1話~第5話 2019.09.09
-
次の記事
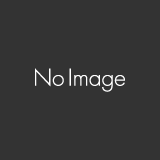
NO SIDE 第13話~第18話 2019.09.12
